FSAM[CGO'16]
Sparse Flow-Sensitive Pointer Analysis for Multithreaded Programs
1. 概要
FSAMのゴール
マルチスレッドプログラムを対象としたFlow-sensitiveなポインタ解析
(Flow-Sensitive pointer Analysis for Multithreaded C programs)
困難
- 無数にあるスレッドインターリーブの扱い
-
並列実行されうるコード部分の算出 in C
- pthreadを用いた同期処理には豊富な表現力がある
- → 正確な解析が困難
- 大規模マルチスレッドプログラムを解析するためのスケーラビリティ
解決策
上記の困難を解決するため,以下の解析アルゴリズムを提案:-
May-Happen-in-Parallel(MHP)解析 in C
- 目的: 並列実行されうるコード部分の算出
- 扱う命令: スレッドの作成/合流(fork/join)
- 精度: Flow-, Context-sensitive
-
Lock解析
-
目的: 他スレッドから干渉されないコード領域の算出
- 考慮すべきスレッドインターリーブを減らせる
- 扱う命令: mutexロックの獲得/解放(lock/unlock)
- 精度: Flow- Context-sensitive
-
目的: 他スレッドから干渉されないコード領域の算出
-
Sparse解析
- 目的: 解析に必要な命令のみ訪問し,解析効率を向上
結果
-
既存手法と比較して
- 解析時間: x12減少
- メモリ使用量: x28減少
-
10万行を超える検体に対してスケール
- 既存手法ではタイムアウト
2. 準備
ポインタ解析
ポインタpがどのオブジェクトを指しうるかを解析
pは何を指す?
1
2
3
4
5
6
int *p, x, y;
p = &x;
...
p = &y;
...
*p;
Flow-insensitive (Compositional style)
プログラムポイントを区別せず,コード全体に対して1つの結果を求める
例:p points-to { x, y }
1
2
3
4
5
6
int *p, x, y;
p = &x;
...
p = &y;
...
*p;
Flow-sensitive (Transitional style)
プログラムポイント毎に結果を求める
例:L.6: p points-to { y }
1
2
3
4
5
6
int *p, x, y;
p = &x;
...
p = &y;
...
*p;
Value-Flowグラフ (Sparse解析)
Def-use chain情報を元に Def → Use へとエッジを貼ったグラフ
Value-Flowグラフを辿ることで,Sparse解析が可能になる.
pに関するvalue-flowグラフ
1
2
3
4
5
6
int *p, x, y;
p = &x;
...
p = &y;
...
*p;

Sparse解析の流れ
-
事前解析(pre-analysis): 高速だが精度の低い解析
- e.g., Flow-insensitiveなポインタ解析
- Value-Flowグラフの構築: 事前解析の結果よりdef-use chainを求め,グラフを構築
-
Sparse解析: Value-Flowグラフ上でより精度の高い解析を実行
- e.g., Flow-sensitiveなポインタ解析
1
2
3
4
5
6
int *p, x, y;
p = &x;
...
p = &y;
...
*p;
Step.1: Flow-insensitiveなポインタ解析
p points-to { x, y }
Step.2: Value-Flowグラフの構築

Step.3: Flow-sensitiveなポインタ解析 on Value-Flowグラフ
p points-to { y }
Motivating Example: マルチスレッドプログラムのポインタ解析
マルチスレッドプログラムに対してSparse解析を行う際,同期処理(fork/join, lock/unlock)の扱いが鍵となる.
1 : int *p, a, b, c, d, e;
2 :
3 : // Thread t0
4 : void main() {
5 : p = &a;
6 : fork(t1, foo);
7 : lock(m);
8 : p = &b;
9 : p = &c;
10: unlock(m);
11: join(t1);
12: *p;
13: }14: // Thread t1
15: void foo() {
16: lock(m);
17: p = &d;
18: p = &e;
19: unlock(m);
20: }
次節では,fork/join, lock/unlockを考慮したValue-Flowグラフ作成アルゴリズムを見ていく.
3. FSAM Approach
FSAMは,Sparse解析の手順に従って解析を行う.
マルチスレッドプログラムを解析する際のポイントは同期処理(fork/join, lock/unlock)の扱いである.
- 事前解析: Flow-insensitive Andersen's pointer analysis
-
Value-Flowグラフの構築
- スレッドのモデル化
- fork/joinを考慮したエッジの追加
- lock/unlockを考慮したエッジの削除
- Sparse解析: Flow-sensitiveポインタ解析 on Value-Flowグラフ
3.1 Static Thread Model
スレッドの作成/合流(fork/join)を考慮するため,モデル化を行う.
行うモデル化は以下:- スレッドのモデル化: スレッド $t$ をどう表現するか
- fork/joinのモデル化: スレッド間のfork/joinをどう表現するか
Abstract Threads
スレッドの抽象化 $t$ はcontext-sensitive fork sitesで表現・区別される.
$t: (c : \text{call-stack}, fk : \text{fork site})$
t0, t1, t2のモデル化
1: // Thread t0
2: void main() {
3: fork(t1, foo);
4: ...
5: join(t1);
6: }7 : // Thread t1
8 : void foo() {
9 : fork(t2, bar);
10: ...
11: join(t2);
12: }13: // Thread t2
14: void bar() {
15: ...
16: }-
t0: ([], null)- mainスレッドのみ,fork siteがない
-
t1: ([], L.3) -
t2: ([L.3], L.9)
Fork/Joinのモデル化
fork/joinは2スレッド間の関係として表現される.
$t \Longrightarrow^{(c, fk)} t'$: コンテクスト$(c, fk)$において,スレッド $t$ が新たなスレッド $t'$ を作成
$t \Longleftarrow^{(c, jn)} t'$ : コンテクスト$(c, jn)$において,スレッド $t'$ がスレッド $t$ へと合流
この関係は推移律を満たす(後述).
例: スレッドt0, t1, t2間のfork/join関係
1: // Thread t0
2: void main() {
3: fork(t1, foo);
4: ...
5: join(t1);
6: }7 : // Thread t1
8 : void foo() {
9 : fork(t2, bar);
10: ...
11: join(t2);
12: }13: // Thread t2
14: void bar() {
15: ...
16: }-
t0 ([], L.3) → t1 -
t1 ([L.3], L.9) → t2 -
t0 ([], L.3) → t2- 上記2つのfork関係による推移律より
-
t0 ([], L.5) ← t1 -
t1 ([L.3], L.11) ← t2 -
t0 ([], L.5) ← t2- 上記2つのjoin関係による推移律より
Siblingスレッド
以下の条件が成り立つ場合,2スレッドをSiblingスレッド $t \bowtie t'$ と定義する:- 2スレッドは同じ親スレッド $t$ を持つ
- 2スレッドのcontext$(c, fk)$が異なる (= 異なる2スレッド)
t1, t2
1: // Thread t0
2: void main() {
3: fork(t1, foo);
4: fork(t2, bar);
5: ...
6: join(t1);
7: join(t2);
8: }9 : // Thread t1
10: void foo() {
11: ...
12: }13: // Thread t1
14: void bar() {
15: ...
16: }
また,Siblingスレッド $t \bowtie t'$ に対して,$t$が合流(join)した後$t'$が生成(fork)される場合,Happens-Before(HB)関係 $t > t'$ が成り立つ.
例:t1 > t2
1: // Thread t0
2: void main() {
3: fork(t1, foo);
4: join(t1);
5: ...
6: fork(t2, bar);
7: join(t2);
8: }9 : // Thread t1
10: void foo() {
11: ...
12: }13: // Thread t1
14: void bar() {
15: ...
16: }
まとめ
スレッドやfork/joinの抽象化により,スレッド間の関係(親子関係,HB関係)が求まる.
以下では,これらの関係を元にValue-Flowグラフを構築していく.
3.2 Thread-Oblivious Def-Useの算出
スレッド間の関係を用いてfork/join命令の前後にあるDef-Useを求める.
複数スレッドを直列化(Thread-Oblivious)して得られるDef-Useは以下の3パターン:-
fork(t1, foo)を関数呼び出しfoo()と解釈して得られるDef-Use -
fork(t1, foo)の前後にあるDef-Use -
スレッド
t1内のDefとjoin(t1)以降のUseで形成されるDef-Use
1 : int *p, a, b, c, d, e;
2 :
3 : // Thread t0
4 : void main() {
5 : p = &a;
6 : fork(t1, foo);
7 : lock(m);
8 : p = &b;
9 : p = &c;
10: unlock(m);
11: join(t1);
12: *p;
13: }14: // Thread t1
15: void foo() {
16: lock(m);
17: p = &d;
18: p = &e;
19: unlock(m);
20: }

fork(t1, foo)を関数呼び出しfoo()と解釈して得られるDef-Use


fork(t1, foo)前後にあるDef-Use (fallthroughエッジ)


t1内のDefとjoin(t1)以降のUseで形成されるDef-Use


今節ではfork/join前後で形成されるDef-Useエッジを作成した.
次節ではより細かいinterleaveを考慮したエッジを作成する.
3.3 Thread-Aware Def-Useの算出
Interleaveを考慮した(Thread-aware) Def-Useエッジを求める.
Thread-aware Def-Useエッジを求める3 Step:- Interleaving解析 (May-Happen-in-Parallel解析): 並列実行される命令列を求める
- Value-Flow解析: interleaveを考慮したDef-Useエッジを張る
- Lock解析: lock/unlockを考慮して,余分なDef-Useエッジを削除
3.3.1 Interleaving解析
並列実行される (May-Happen-in-Parallel(MHP)関係にある) 命令列を求める.
アルゴリズム
制御フロー(CFG + fork/join関係)に沿った,データフロー解析:- 方向: 前向き
-
Domain: スレッドの集合
- 収集する情報: 並列実行されるスレッド
- Transfer functions: 以下の具体例で説明
1: // Thread t0
2: void main() {
3: s1;
4: fork(t1, foo);
5: s2;
6: join(t1);
7: s3;
8: }9 : // Thread t1
10: void foo() {
11: s4;
12: }
CFG + fork/join関係

意味: 並列実行されるスレッドなし

$ t \Longrightarrow t' $:
-
$ OUT_t = IN_t \cup \{t'\} $
- $ IN_{t'} = IN_t \cup \{t\} $
例: t0: fork(t1, foo)
- $ IN_{s2} = \{ \} \cup \{ t1 \} $
- $ IN_{s4} = \{ \} \cup \{ t0 \} $

$ t \Longleftarrow t' $
- $ OUT_t = IN_t \setminus \{ t' \} $
例: t0: join(t1)
- $ OUT_{join(t1)} = \{ t1 \} \setminus \{ t1 \} = \phi $




3.3.2 Value-Flow解析
MHP関係を用いて,Value-Flowグラフにinterleaveを考慮したDef-Useエッジを追加する.
以下の条件に合致するノード間にDef-Useエッジを追加する:- 2命令が同じ変数へのアクセス命令であり,少なくとも片方が定義
- 2命令が並列実行されうる
例: Motivating Example
作成途中のValue-Flowグラフ

Interleaving解析の結果

p = &b, p = &c } ⇄ { p = &d, p = &e } というエッジが張られる.
Interleaveによるエッジを追加

しかし,実はこのValue-Flowグラフには余計なエッジが含まれている.


p = &b → { p = &d, p = &e }
p = &d → { p = &b, p = &c }
p = &c ⇆ p = &e
計6本

冗長なエッジを削除するため,mutexロックの確保/解放(lock/unlock)を解析する.
3.3.3 Lock解析
mutexロックで保護された命令列はアトミック(他スレッドから非干渉)である性質を考慮し,冗長なDef-Useエッジを削除する.
mutexロックで保護された命令列は,以下の3つで定義される:-
Lock-Release Span $sp_m$:
lock(m)からunlock(m)までの範囲 - Span Head $HD(sp_m, o)$: $sp_m$の先頭時点のオブジェクト$o$にアクセスする命令の集合
- Span Tail $TL(sp_m, o)$: $sp_m$の末尾時点のオブジェクト$o$を定義する命令の集合
3つの定義を用いて,$sp_m$内の命令列を1つのノードとして見なし,
- どの変数を使用($HD(sp_m, o)$)し,
- どの変数を定義($TL(sp_m, o)$)するか

Lock-Release Span
目的: lock(m)からunlock(m)までの命令列
性質: context-sensitiveなスレッド$t: (c, fk)$で解析
→ context-sensitive

Span Head
目的: Spanの先頭時点のオブジェクトにアクセスする命令の集合
例:p = &b; in t0含まれない例:
p = &c; in t0∵ 先頭時点の
pにはアクセスしないため

Span Tail
目的: Spanの末尾時点のオブジェクトを定義する命令の集合
例:p = &c; in t0含まれない例:
p = &b; in t0∵ 末尾時点では上書きされ,到達しないため

冗長なDef-Useエッジ
以下の条件が成立する場合,Def-Useエッジが冗長:- 同じmutexロックで保護されている and
-
どちらかが成り立つ:
- DefがSpan Tailに含まれない or
- UseがSpan Headに含まれない
定義が末尾に到達しないDef or 先頭で使用しないUseによるDef-Useエッジを冗長として削除する.
-
p = &b→{ p = &d, p = &e }- ∵
p = &b$\notin$TL(p) in t0
- ∵
-
p = &d→{ p = &b, p = &c }- ∵
p = &d$\notin$TL(p) in t1
- ∵
-
p = &c→p = &e- ∵
p = e$\notin$HD(p) in t1
- ∵
-
p = &e→p = &c- ∵
p = &c$\notin$HD(p) in t0
- ∵
TL(p) → HD(p):
-
p = &c→p = &d -
p = &e→p = &b

3.3 Thread-Aware Def-Useの算出 まとめ
(再掲) Thread-aware Def-Useエッジを求める3 Step:- Interleaving解析 (May-Happen-in-Parallel解析): 並列実行される命令列を求める
- Value-Flow解析: interleaveを考慮したDef-Useエッジを張る
- Lock解析: lock/unlockを考慮して,余分なDef-Useエッジを削除

3.4 Sparse解析
求まったValue-Flowグラフ上で,Flow-sensitiveなポインタ解析を行う.
アルゴリズムはsequentialプログラムに対するものと同じ.




4. 評価
- 実験環境: 2.70GHz Intel Xeon Quad Core CPU, 64GB memory, Ubuntu Linux
- 実装: LLVM-3.5ベース, Andersenのポインタ解析(事前解析)
-
比較研究: 既存研究を組み合わせたNonSpase解析の再現実装
- RR[PLDI'99]: Cilk(並列計算用の拡張C)を対象としたFlow-sensitiveなポインタ解析
- PCG[POPL'11]: MHP解析 for pthread
- 自作した理由: C言語,pthread対応のFlow-sensitiveなポインタ解析がないため
- 検体: 10個のCプログラム
| Benchmark | LOC |
|---|---|
| word_count | 6330 |
| kmeans | 6008 |
| radiosity | 12781 |
| automount | 13170 |
| ferret | 15735 |
| bodytrack | 19063 |
| httpd_server | 52616 |
| mt_daapd | 57102 |
| raytrace | 86373 |
| x264 | 113481 |
- RQ.1: 既存研究(NonSparse)と比較し,FSAMの解析時間・メモリ使用量はどの程度か?
-
RQ.2: FSAMが提案する3つの解析アルゴリズムは解析時間にどう影響するか?
- Interleaving解析: 既存研究PCG[POPL'11]と比較
- Value-Flow解析: 解析あり と なし を比較
- Lock解析: 解析あり と なし を比較
実験1 FSAM vs. NonSparse(RR + PCG)
| Program | Time(s) | Memory(MB) | ||
|---|---|---|---|---|
| FSAM | NonSparse | FSAM | NonSparse | |
| word_count | 3.04 | 17.40 | 13.79 | 53.76 |
| kmeans | 2.50 | 18.19 | 18.27 | 53.19 |
| radiosity | 6.77 | 29.29 | 38.65 | 95.00 |
| automount | 8.66 | 83.82 | 27.56 | 364.67 |
| ferret | 13.49 | 87.10 | 52.14 | 934.57 |
| bodytrack | 128.80 | 2809.89 | 313.66 | 12410.16 |
| httpd_server | 191.22 | 2079.43 | 55.78 | 6578.46 |
| mt_daapd | 90.67 | 2667.55 | 37.92 | 3403.26 |
| raytrace | 284.61 | OOT | 135.06 | OOT |
| x264 | 531.55 | OOT | 129.58 | OOT |
| Ave. | 12x faster | 28x less | ||
まとめ: 10万行程度のCプログラムに対して,効率よく解析可能
実験2: FSAMが提案する3つの解析による影響
- No-Interleaving(MHP解析): 既存手法PCGによるMHP解析で代替
-
No-Value-Flow: Value-Flowを考慮せず,エッジを張る
- 本来はDef-Use関係にないノード間にもエッジが張られてしまう
- No-Lock: mutexロックを考慮せず,冗長なDef-Useエッジが含まれる
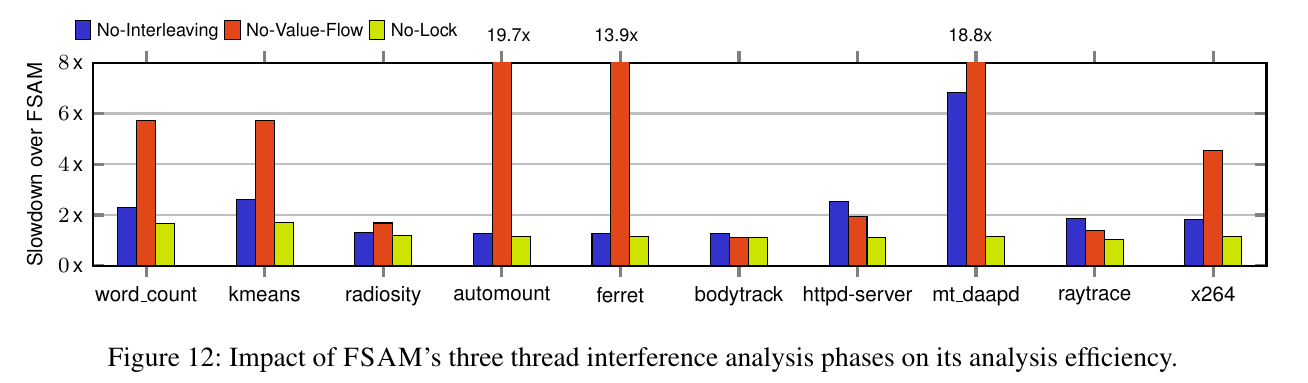
- No-Interleaving: 既存手法と比較し,fork/joinを適切に対処し,正確なMHP関係が求められる
- No-Value-Flow: Def-Use関係にあるノード間にのみエッジを張ることで,大部分のインターリーブを削減できる
- No-Lock: mutexロックを考慮し,冗長なインターリーブを削減できる
6. まとめ
-
目的: マルチスレッドプログラムを対象としたFlow-sensitiveなポインタ解析
- Flow-Sensitive pointer Analysis for Multithreaded C programs
-
マルチスレッドプログラムに対応したValue-Flowグラフを作る3つのアルゴリズム:
- Interleaving解析(MHP解析): 並列実行される命令列を特定
- Value-Flow解析: MHP関係にある and Def-Use関係にあるノード間にエッジ追加
- Lock解析: mutexロックを考慮し,冗長なエッジを削除
-
結果
-
既存手法と比較して
- 解析時間: x12 faster
- メモリ使用量: x28 less
- 10万行を超える検体に対してスケール
-
既存手法と比較して
7. 提案手法との関連
提案手法の目的: メモリ保護 + 並行バグ検知提案手法の流れ:
- 静的Def-Use解析: 合法なDef-Use関係を計算
- 保護プログラムの計装: 実行時のDef-Use関係を監視するチェックコードを挿入
- 実行時チェック: 実行時に違法なDef-Useを検知
-
利用する解析結果1: Value-Flowグラフ for Multithreaded Programs
- SoundなValue-Flowグラフ上で,Reaching Definitions解析を行い,合法なDef-Use関係を得る
- SVFフレームワーク上に実装されており,Field-sensitivityもある
-
利用する解析結果2: MHP解析 + Lock解析
-
データレースの関係にあるDef-Useを以下の条件より判定:
- 2命令がMHP関係にある
- 同一のロックで保護されていない
-
データレースであるDef-Useを非合法として扱い,実行時にはデータレース検知も行う
- データレースの誤検知が多くなる恐れあり
-
データレースの関係にあるDef-Useを以下の条件より判定:
Q&A
Q. なぜスレッドモデルにcall-stackが必要?
A. スレッドを正確に区別したいため
1 : // Thread t0
2 : void main() {
3 : foo(); // create t1
4 : foo(); // create t2
5 : }
6 :
7 : void foo() {
8 : fork(t);
9 : join(t);
10: }同じfork-siteだが,2つのスレッドを区別:
-
t1: ([L.3], L.8) -
t2: ([L.4], L.8)
Q. forループ内のforkはどう扱う?
A. スレッドにMulti-Forkedである情報を持たせ,そのスレッド内にある命令列は全てMHP関係にあると判定
0: // Thread t0
1: void main() {
2: for (int i = 0; i < 8; i++)
3: fork(t[i], foo);
4:
5: for (int i = 0; i < 8; i++)
6: join(t[i]);
7: }8 : // Thread t[i] (Multi-Forked)
9 : void foo() {
10: p = &x;
11: p = &y;
12: }スレッドモデル: LLVM SCEV(ScalarEvolutionAliasAnalysis)により,固定数スレッドに対して,正確にfork/joinを算出

MHP関係: スレッドt[i]内のコードは全て相互にMHP関係
(Interleave解析において,並列実行されるスレッドに自身のスレッドt[i]を加えたと解釈しても良い)
- L.10 || L.10
- L.10 || L.11
- L.11 || L.11
Value-Flowグラフ

Q. 多段fork/joinの扱い
A. 多段fork/joinを考慮したスレッド間の関係を用いて,MHP関係にあるスレッドを収集
t0のfork関係:
t0$\Longrightarrow$t1-
t0$\Longrightarrow$t2-
t1$\Longrightarrow$t2との推移律より
-

t1のfork関係:
t1$\Longrightarrow$t2
